女性たちによると、ジェンダーに関するマイクロアグレッションは頻繁に生じており、自らの貢献の価値を適切に認めてもらえていなかったり、性的な対象にされてしまったり、業績を低く見積もられたり、社会や教育や職場や専門的な環境において影響力を持つことを制限されたりしている。例えば仕事の世界において、多くの女性は男性の同僚から、見下されたり、失礼な態度をとられたり、提案を却下されるというお決まりのパターンを口にする。会議の間、女性社員があるアイデアを出したとしても、男性のCEOはそれに反応しなかったり、聞こえなかったふりをしたりすることがある。しかし、男性の同僚が同じような発言をすると、彼は執行部や同僚の前で認められ、称賛されるのだ。このようなことは教室でもよく見られる。男子生徒は女子生徒よりも頻繁に、発言することや問いに答えることを教師に求められる。これらのマイクロアグレッションに込められた隠れたメッセージは、女性のアイデアや貢献は男性のそれと比べて、価値が低いということだ。
カトリーヌの面接のエピソードにおいて、いくつかのジェンダーに関するマイクロアグレッションが、善意の男性の乗客や面接官からなされている。
まず、魅力的な若い女性にとって男性たちからうっとりとした目でみられることは珍しいことではない。地下鉄に乗り込んだ時、カトリーヌは男性の乗客たちから投げかけられた視線に気づいた。彼女は人から注目されていることはまんざらでもないようであったが同時に「いやらしい」視線も感じた。異性にとって魅力的でありたいし、モテたい一方で、性の道具として扱われてしまうことが苦しいという二重の感覚は、時に女性たちが直面する矛盾を孕んだ感覚といえる。女性を性的な道具のように扱うあからさまな表現は、口笛を吹くことやひやかしに始まり、もっとかすかな、例えば公共の場でまるで衣服を脱がされたような気持ちにさせる「凝視」まで、幅がある。
二つ目に、先の男性の乗客がよかれと思って「囚われの姫君」を自由にしようとカトリーヌの腰に手を回し出口に案内したことは、彼女のバーソナルスペースに対する侵入であったといえる。赤の他人が、女性の背中に少し触ったり、あるいはもっとずうずうしく通りすがりに本人の許可無くおしりを触ったりすることは、身体的暴行だとみなされるだろう。女性を性的な道具と見なすマイクロアグレッションが伝えているメッセージは多い。それは、(a)女性の見た目は男性を楽しませるために存在する、ということや、(b)女性とは弱くて、依存的で、助けを必要とする、ということ、(c)女性の身体は彼女自身のものではない、ということだ。女性の中にはこのような屈辱的な行動に、傷つけられる人もいる。しかしカトリーヌを助けようとした男性は、おそらく誠心誠意行動したのだろう。
三つ目に、女性の社員を下の名前で読んだり、例えばカトリーヌを「キャシー」と勝手に愛称で呼んだりすることは、男性の社員に同じようにする場合に比べて、「失礼だ」とは思われにくいだろう。他方で、副部長は男性たちに対してはもっと礼儀正しく苗字に「さん」をつけて呼んでいた。そして副部長は、(たとえそれが冗談であったとしても)仕事よりも彼女の面倒をみてくれる「イイ男」の方が必要であると暗に示すことによって、女性は結婚しなければならず、彼女たちの居場所は家にあり、男性に面倒をみられなければならず、カトリーヌが家族を支えなければいけない男性から仕事を奪う可能性がある、といったマイクロアグレッションに満ちたメッセージを送っていた。カトリーヌと副部長の間でかわされたこの自然で短い一連のやりとりは、仕事を見つけたいという彼女の欲求をつまらないものとみなし、あたかもカトリーヌを子どものように扱い、将来有望な人としては真剣に見ていない、といったことを示していた。
四つ目に、採用基準を聞かれた時、副部長は「最もその仕事にふさわしい人」だと答えた。この答えは、誰もが平等に扱われており、ジェンダーでは区別されず、雇用において均等な機会をもっており、「みな同じ人間」である、といったことを示している。非常に興味深いことに、先ほどのやりとりだけから、カトリーヌは自分が採用されないであろうと結論づけた。これを行き過ぎた結論であると言うのは簡単なことである。しかしむしろ私たちにとって大切なことは、どのようにしてカトリーヌがそのように強く信じるに至ったのかを考えることだ。第2章で論じるように、副部長の応答はこの社会における女性の立場に関する世界観を反映している。「最もふさわしい人が採用されるべきだ」といった発言を仕事の面接の場において聞く多くの女性たちは、これをジェンダーにおけるマイクロアグレッションだと感じる。それはこの発言に、「女性は男性よりもふさわしくない。だから男性の志願者が選ばれたとしても、それは偏見とはなんの関係もなく純粋に彼の資質によるものだ」という意味が込められているからだ。この副部長の発言は、彼はジェンダーに基づく偏見を持つことなど不可能だと暗に示している。なぜなら、彼にとっては「ジェンダーなど関係ない」(gender-blind)のだから。同じような現象はカラーブラインドの神話について、有色人種の人々からも言われている。ジェンダーによる差別の存在を否認することは、女性の経験してきた実感を否認し、男性に自分たちが特権的立場にあることを否認させてしまうマイクロアグレッションであるということに副部長は気づいていない。
Sue, Derald Wing, 2010, Microaggressions in everyday life: race, gender, and sexual orientation, Hoboken, N.J.: Wiley. (マイクロアグレッション研究会訳,2020,『日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション : 人種、ジェンダー、性的指向:マイノリティに向けられる無意識の差別』明石書店.)pp.44-6
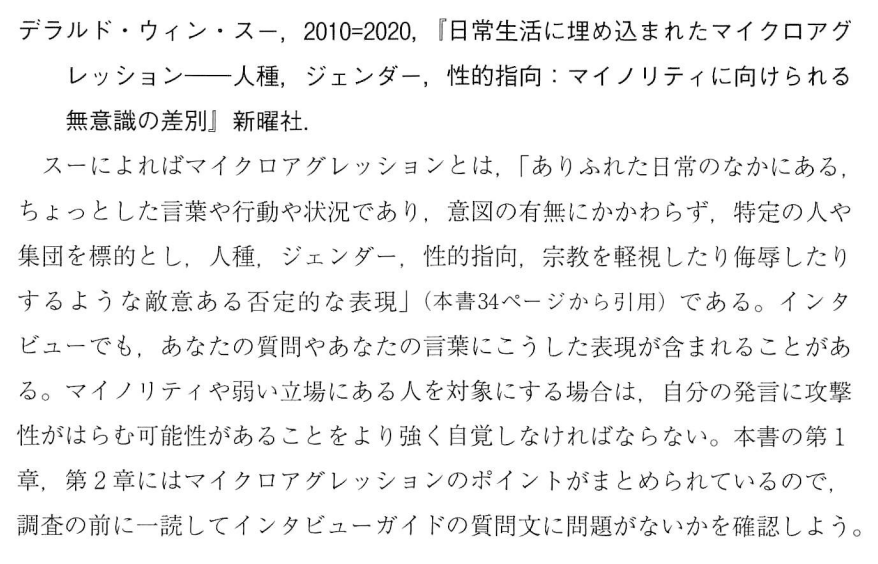
山口富子編,2023,『インタビュー調査法入門——質的調査実習の工夫と実践』ミネルヴァ書房.P.217